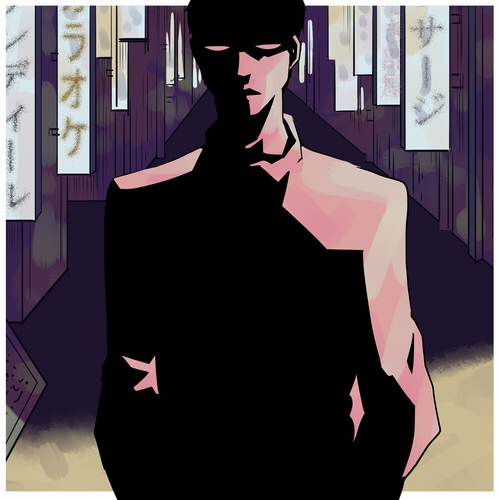第十八話
「電話なら出ていいぞ」
有田が言った。
「いや、大丈夫です」
「どうして出ないんだい。まさか女か、柏木君。オレに聞かれちゃあマズい電話かな」
いつもの有田なら、撮影中に柏木が電話に出ることなど許すはずもない。柏木は「何で今日に限って、クソ有田が」と思ったが、他にどうすることもできず、通話のボタンを押した。
「やぁ、ゆきさん。今夜、そっちに行くんだが、時間作ってもらえないだろうか」
すでに汗を噴き出していた柏木の額から、大粒の汗が流れ落ち、その一部が眉を通過して目に入った。
電話に出てしまったものの、今ここで、女装子のように裏返った声で返事をするわけにはいかない。
柏木は滲みる目を曲げた右手の人差し指で押さえながら、何も言わずに電話を切った。
「先生」からの電話を無碍に切ってしまった。
「もうこれで、二度と女とセックスするチャンスは巡ってこない」柏木は心の中でそう呟いた。
有田は、3人目のОLを撮り始めていた。
「キミも、キャバでバイトしてるのかな。目が艶っぽくていいね店に出てるとしたら、ナンバーワンだろう」
相変わらず調子がいい。
柏木は、そんな有田の後ろで着信履歴をこっそりと見た。
後から電話してみようか。「先生」は怒っていないだろうか。
「先生」と会えば、また女とセックスできるかも知れない。
柏木は、半年前に太田のラブホテルでナースとセックスした時の情景を、明け方の夢を思い出す時のように、断片的に脳裏に浮かべていた。
まさに夢のようなひと時だった。自分のイチモツが、女のアノ部分に深く埋まり、その中で果ててしまったことが、今でも信じられない。
女装子になれば、男にモテるから、男の口の中で射精することは簡単なことだった。だが、柏木にとって女とセックスすることは、その何百倍も難しい、不可能に近いことだった。
そんな時、有田のカメラのファインダーに映っていたОLが、
「私、キャバじゃなくて風俗です」
と、言った。
「もちろん会社には秘密だよね。だって、一部上場の本社勤務でしょ。やるなぁ、ОLさんは。デリなの?」
有田の問い掛けに、ОLは、
「吉原です」
と、答えた。
吉原が、ソープを意味することや、ソープでは、客が風俗嬢とセックスまですることは、柏木にも分かった。
金さえ払えば、目の前のОLとセックスできるのか。26歳だというそのОLは、森カンナに似ていた。柏木が半年前にセックスしたナースも山本美月に似た美女だったが、目の前のОLも、相当にいい女だ。
だが、柏木に、そのОLとセックスするためにソープに行く度胸など、あるはずがなかった。
「マジなの?じゃあ、オレ、指名で行くよ。次、いつ出勤なの?」
有田は、何の迷いもなく、ОLにそう言い放った。
「今夜です」
「じゃあ、今夜行くから。決まりね。絶対行くから、生でヤラせて」
「いいですよ。ピル飲んでるから」
柏木が半年前の思い出に浸っている間に、有田とОLは、事実上のセックスをする約束をしてしまっていた。
柏木は、「有田、死ね」と、心の中で叫ぶことしかできなかった。
「柏木君も一緒に行くか。なんならソープ奢ってやってもいいぞ」
有田は、カメラのシャッターを押しながら柏木の方を振り返りもせずにそう言った。
「いや、いいです」と断ることを前提に、有田がからかっていることは、柏木には分かっていた。
上野駅西口のペデストリアルデッキを吹き抜ける夜の風には、もう夏の匂いは残っていなかった。
街行く人の中には、まだ半袖姿の人もちらほらいたが、鼻腔の奥に、金木犀の匂いすら感じた。
そう言えば、ちょうど1年前、池袋のミストで有田のイチモツを咥えた夜も金木犀の匂いが漂っていたことを柏木は思い出した。
今頃、有田は、ソープに行って、あのОLと繋がり合っているのだろうか。
その夜、柏木はミストへ行こうと思っていたが、女装子になって、男とイチモツを咥えたり咥えられたりすることが情けなく感じた。
やっぱり「先生」に電話してみよう。
そう心の中で思いながらも、地下鉄銀座線に行き先も決めずに乗った柏木は、日本橋でも新橋でも降りずに、赤坂見附で、ホームの向かいに停まっていた赤い車輌に乗り換えた。
柏木は丸の内線の電車を、新宿三丁目で降りた。
足は歌舞伎町に向かっていた。
花園神社の脇からゴールデン街を抜け、新宿区役所の裏手に拡がる猥雑なエリアをフラフラと歩いた。
ようやく足を止めたのは、『グランディール』というキャバクラの前だった。
昼間の撮影で2人目のモデルだったОLがアルバイトをしていると言っていた店だ。
三日後に皆既月食を迎えることになっている月がビルとビルの隙間から柏木の頬を照らしていたが、夜の看板に目が眩んでいた柏木は、それに気付くことはなかった。
ツイート

- 志井愛英
- 小説家。昭和41年生まれ。同性愛者、風俗嬢、少数民族、異端芸術家など、マイノリティを題材にした作品が多い。一部の機関誌のみでしか連載しておらず、広く一般に向けた作品は本篇が初。
瞑想サウナ記事一覧
カチカチ丘コラム一覧
- ヘッジファンドに情報を売る男
- 今夜、すべてのクロッチを
- 瞑想サウナ
- 竹光殺法じゅて~むで候
- オナホール戦記W
- 伊藤MILK!
- 日本の沼
- それイけ! チンチンカモカモ
- 復活!日本ミニスカ倶楽部
- ナマ漫画
- 竿に訊け
- 爆発映画のススメ
- なぜ中年男性が女子小中学生~
- 第一回 「綿100%、ピコレース付きの純白パンツ」
- 第二回 「3年間同棲した彼女のパンツ」
- 第三回 「あいだゆあのピンクのTバック」
- 第四回 「アメコミ風の柄が一面に描かれた派手なパンツ」:前編
- 第五回 「アメコミ風の柄が一面に描かれた派手なパンツ」:後編
- 第六回 「囮の妻のパンツ」
- 第七回 「私的パンティジャケットベスト10」
- 第八回 「さくらのパンティ」
- 第九回 「恋のシュビドゥパンツ」
- 第十回 「地球の裏側のパンツ泥棒事情」
- 第十一回 「好きなコはできた」
- 第十二回 『The Times They Are a-Changin’(時代は変る)』
- 第十三回 「Too Much Panty Business」
- 第十四回 「コロナ鬱とコロナ躁」
- 第一回 「あこがれのセーラーちゃん」
- 第二回 「セックスの世界観」
- 第三回 「ぴことちこ」「さとあな」
- 第四回 「フェラホール」
- 第五回 「オナホ女子のオナホ女子会(1/5)」
- 第六回 「オナホ女子のオナホ女子会(2/5)」
- 第七回 「オナホ女子のオナホ女子会(3/5)」
- 第八回 「オナホ女子のオナホ女子会(4/5)」
- 第九回 「オナホ女子のオナホ女子会(5/5)」
- 第十回 「オナホ超飲み会現場レポート」
- 第十一回 「ジ・オナホポエム 〜 オナホパッケにおける文章の力」
- 第十二回 「パロディホール」
- 第十三回 「第二部 序文」
- 第十四回 「皮オナ期のちんちんへ」
- 第十五回 「奨学金をオナホにつぎ込んだエロ大学生」
- 第十六回 「NASAの最先端無毛ツルツルまんこ」
- 第十七回 「ハルミデザインズとアメリカ製Real Dollのラブドール」
- 第十八回 「ココナツオナホ」
- 第十九回 「オナーパンツ」
- 第二十回 「家電でオナマシン【GuWOOO】」
- 第二十一回 「コバヤシ君」
- 第二十二回特別編 「器具田教授に17の質問」
- 第二十三回 「アダルトVRフェスタ」
- 第一回 「マリークワントとツィッギー」
- 第二回 「麻生真美子」
- 第三回 「皇太子ご成婚報道パンチラ 田丸美寿々」
- 第四回 「スカイマークのミニスカ制服」
- 第五回 「キャサリン妃、至る所で捲れ上がるスカート」
- 第六回 「熟女ミニスカ推進派の星、 NHKアナ有働由美子、再び勝負しろ」
- 第七回 「美脚パンチラの闘士、米倉涼子 期待を裏切らない超ミニ・パンチラ」
- 第八回 「元宝塚、和央ようか46歳、 先輩女優を凌駕する 貫禄の激烈ミニ&悩殺パンチラ」
- 第九回 「菜々緒、プールでビキニのお約束ポーズよりも数倍エッチに悩殺、ビキニとミニスカのコラボ」
- 第十回 「2014年ミス・インターナショナル世界大会は日本で開催」
- 第十一回 「真矢みき・50歳偉丈夫が繰り出した切り札パンチラ」
- 第十二回 「テレ朝のエース候補だった才色兼備の女子アナ 野村真季の残念な凋落」
- 第十三回 「元ヤンキー、佐々木希はパンチラを捨て ダイコン女優から演技派に開眼か!?」
- 第十四回 「吉瀬美智子 40歳で取材記者騒然の超ミニ・パンチラなのに翌日は報道規制の圧力で地味写真ばかり」
- 第十五回 「おいおい、台湾で開催されるモーターショーはとんでもないことになってるぞ」
- 第十六回 「かとうれいこ一日署長が魅せた熟れたミニスカ」
- 第十七回 「片瀬那奈、NHKドラマ会見でパンチラ勃発もネット画像で広まった写真は皆無…の謎」
- 第十八回 「フジテレビの女帝、乳出し熟女アナ阿部智代 遂にアナウンサー復帰ならず、引退」
- 第十九回 「さすが五輪招致の功労者、鉄壁の防御でこれが限界か、滝川クリステル」
- 第二十回 「あの上昇志向の塊、皆藤愛子がお堅い番組に超ミニ出演でパンチラ」
- 第二十一回 「フリーアナウンサー美馬怜子 武豊に仕掛けたハニートラップ策略 世間にバレバレ、非難のド壷」
- 第二十二回 「清純演技派の石田ゆり子にこの翳りの透けるエロパンティを 穿かせたのは誰だ…」
- 第二十三回 「祝!北川景子、ご結婚パンチラ 共演者キラーの勲章を返上」
- 第二十四回 「歌姫・浜崎あゆみ、チラリどころかテレビ史上最大のパンティ面積を公開」
- 第二十五回 「小林麻耶、36歳のブリッコ超ミニ・熱烈応援」
- 第二十六回 「長澤まさみ、伊勢谷友介と破局で 再びミニスカ魂に火が着いた!」
- 第二十七回 「2016世相ブラ発表 あまりにも下半身がなおざりですよ」
- 第二十八回 「アメリカのアイスホッケーは肉弾戦だが試合途中の氷上整備は超ミニで息抜き」
- 第二十九回 「伊勢谷友介と破局してから やっぱりエロ全開の長澤まさみ」
- 第三十回 「ザイナ・ドリディと三田佳子」
- 第一回 「私のネタ作り」
- 第二回 「外でシコる」
- 第三回 「死者でシコれるか」
- 第四回 「偽装問題」
- 第五回 「人間に生まれて」
- 第六回 「息子がシコりまくっていたら」
- 第七回 「乳を吸うのはかっこ悪い?」
- 第八回 「Facebook」
- 第九回 「女に生まれ変わったら」
- 第十回 「シャブSEX」
- 第11回 「ワールドカップ」
- 第12回 「夏場は特にお気をつけください」
- 第13回 「ここにキスして」
- 第14回 「心霊写真」
- 第15回 「抜き差しならない」
- 第16回 「マンコ」
- 第17回 「ニュース」
- 第18回 「細い脚」
- 第19回 「マン毛」
- 第20回 「娘がヤリマンだったら」
- 第二十一回 「オナニー」
- 第二十二回 「ヘヴィメタル」
- 第二十三回 「便意」
- 第二十四回 「妄想SEX」
- 第二十五回 「報道被害」
- 第二十六回 「春画」
- 第二十七回 「夢精」
- 第二十八回 「再生」
- 第二十九回 「抱負」
- 第三十回 「ベッキー」
- 第一回 「綿100%、ピコレース付きの純白パンツ」
- 第二回 「3年間同棲した彼女のパンツ」
- 第三回 「あいだゆあのピンクのTバック」
- 第四回 「アメコミ風の柄が一面に描かれた派手なパンツ」:前編
- 第五回 「アメコミ風の柄が一面に描かれた派手なパンツ」:後編
- 第六回 「囮の妻のパンツ」
- 第七回 「私的パンティジャケットベスト10」
- 第八回 「さくらのパンティ」
- 第九回 「恋のシュビドゥパンツ」
- 第十回 「地球の裏側のパンツ泥棒事情」
- 第十一回 「好きなコはできた」
- 第十二回 『The Times They Are a-Changin’(時代は変る)』
- 第十三回 「Too Much Panty Business」
- 第十四回 「コロナ鬱とコロナ躁」
- 第一回 「あこがれのセーラーちゃん」
- 第二回 「セックスの世界観」
- 第三回 「ぴことちこ」「さとあな」
- 第四回 「フェラホール」
- 第五回 「オナホ女子のオナホ女子会(1/5)」
- 第六回 「オナホ女子のオナホ女子会(2/5)」
- 第七回 「オナホ女子のオナホ女子会(3/5)」
- 第八回 「オナホ女子のオナホ女子会(4/5)」
- 第九回 「オナホ女子のオナホ女子会(5/5)」
- 第十回 「オナホ超飲み会現場レポート」
- 第十一回 「ジ・オナホポエム 〜 オナホパッケにおける文章の力」
- 第十二回 「パロディホール」
- 第十三回 「第二部 序文」
- 第十四回 「皮オナ期のちんちんへ」
- 第十五回 「奨学金をオナホにつぎ込んだエロ大学生」
- 第十六回 「NASAの最先端無毛ツルツルまんこ」
- 第十七回 「ハルミデザインズとアメリカ製Real Dollのラブドール」
- 第十八回 「ココナツオナホ」
- 第十九回 「オナーパンツ」
- 第二十回 「家電でオナマシン【GuWOOO】」
- 第二十一回 「コバヤシ君」
- 第二十二回特別編 「器具田教授に17の質問」
- 第二十三回 「アダルトVRフェスタ」
- 第一回 「マリークワントとツィッギー」
- 第二回 「麻生真美子」
- 第三回 「皇太子ご成婚報道パンチラ 田丸美寿々」
- 第四回 「スカイマークのミニスカ制服」
- 第五回 「キャサリン妃、至る所で捲れ上がるスカート」
- 第六回 「熟女ミニスカ推進派の星、 NHKアナ有働由美子、再び勝負しろ」
- 第七回 「美脚パンチラの闘士、米倉涼子 期待を裏切らない超ミニ・パンチラ」
- 第八回 「元宝塚、和央ようか46歳、 先輩女優を凌駕する 貫禄の激烈ミニ&悩殺パンチラ」
- 第九回 「菜々緒、プールでビキニのお約束ポーズよりも数倍エッチに悩殺、ビキニとミニスカのコラボ」
- 第十回 「2014年ミス・インターナショナル世界大会は日本で開催」
- 第十一回 「真矢みき・50歳偉丈夫が繰り出した切り札パンチラ」
- 第十二回 「テレ朝のエース候補だった才色兼備の女子アナ 野村真季の残念な凋落」
- 第十三回 「元ヤンキー、佐々木希はパンチラを捨て ダイコン女優から演技派に開眼か!?」
- 第十四回 「吉瀬美智子 40歳で取材記者騒然の超ミニ・パンチラなのに翌日は報道規制の圧力で地味写真ばかり」
- 第十五回 「おいおい、台湾で開催されるモーターショーはとんでもないことになってるぞ」
- 第十六回 「かとうれいこ一日署長が魅せた熟れたミニスカ」
- 第十七回 「片瀬那奈、NHKドラマ会見でパンチラ勃発もネット画像で広まった写真は皆無…の謎」
- 第十八回 「フジテレビの女帝、乳出し熟女アナ阿部智代 遂にアナウンサー復帰ならず、引退」
- 第十九回 「さすが五輪招致の功労者、鉄壁の防御でこれが限界か、滝川クリステル」
- 第二十回 「あの上昇志向の塊、皆藤愛子がお堅い番組に超ミニ出演でパンチラ」
- 第二十一回 「フリーアナウンサー美馬怜子 武豊に仕掛けたハニートラップ策略 世間にバレバレ、非難のド壷」
- 第二十二回 「清純演技派の石田ゆり子にこの翳りの透けるエロパンティを 穿かせたのは誰だ…」
- 第二十三回 「祝!北川景子、ご結婚パンチラ 共演者キラーの勲章を返上」
- 第二十四回 「歌姫・浜崎あゆみ、チラリどころかテレビ史上最大のパンティ面積を公開」
- 第二十五回 「小林麻耶、36歳のブリッコ超ミニ・熱烈応援」
- 第二十六回 「長澤まさみ、伊勢谷友介と破局で 再びミニスカ魂に火が着いた!」
- 第二十七回 「2016世相ブラ発表 あまりにも下半身がなおざりですよ」
- 第二十八回 「アメリカのアイスホッケーは肉弾戦だが試合途中の氷上整備は超ミニで息抜き」
- 第二十九回 「伊勢谷友介と破局してから やっぱりエロ全開の長澤まさみ」
- 第三十回 「ザイナ・ドリディと三田佳子」
- 第一回 「私のネタ作り」
- 第二回 「外でシコる」
- 第三回 「死者でシコれるか」
- 第四回 「偽装問題」
- 第五回 「人間に生まれて」
- 第六回 「息子がシコりまくっていたら」
- 第七回 「乳を吸うのはかっこ悪い?」
- 第八回 「Facebook」
- 第九回 「女に生まれ変わったら」
- 第十回 「シャブSEX」
- 第11回 「ワールドカップ」
- 第12回 「夏場は特にお気をつけください」
- 第13回 「ここにキスして」
- 第14回 「心霊写真」
- 第15回 「抜き差しならない」
- 第16回 「マンコ」
- 第17回 「ニュース」
- 第18回 「細い脚」
- 第19回 「マン毛」
- 第20回 「娘がヤリマンだったら」
- 第二十一回 「オナニー」
- 第二十二回 「ヘヴィメタル」
- 第二十三回 「便意」
- 第二十四回 「妄想SEX」
- 第二十五回 「報道被害」
- 第二十六回 「春画」
- 第二十七回 「夢精」
- 第二十八回 「再生」
- 第二十九回 「抱負」
- 第三十回 「ベッキー」